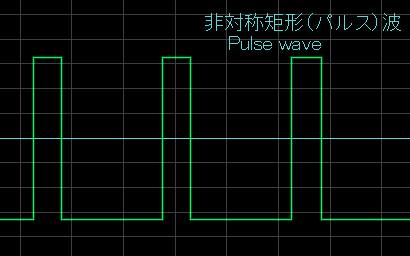|
さて、ファミコンに内蔵されているシンセサイザーですが、手許に正確な資料がないため、憶測で書かなければならない箇所がいくつかあります。もし資料をお持ちの方がいらっしゃいましたら、筆者までご連絡下さるよう、よろしくお願いいたします。 ファミコンに搭載されているデジタル・シンセサイザーは、基本的に4つの音を同時に鳴らすことができます。とはいえ、その各音が好きな波形を合成できるわけではなく、以下のように分けられることになります。
このように、シンセサイザー内で「発音」を請け負う部分を、「オシレータ」と呼びます。ファミコンに搭載されているシンセは、音量、音程などの情報をデジタル的に(=ICで処理された具体的な数値で)扱うので、4DCO(Digital Controled Oscilator)のシンセと考えてよいでしょう。 なお、矩形波を担当する2つのオシレータは、正確には「非対称矩形波(もしくはパルス波 Pulse wave)」オシレータといえます。 これは何かというと、電圧が最高になる時間と最低になる時間の比率(パルス幅)を変化させることによって、音色を変えられるようになっているものです。
このように一定の音数、決められた波形しか使用できないのは、非常に自由度が低いように思われますが、機能の特化されたチップを使用することは、コンピュータの脳であるCPUの仕事を減らす上で、非常に合理的な方法だったのです。 このような波形を合成できるチップを別に用意すれば、CPUは「音程・音量」というわずか二つのパラメータを、4つあるオシレータのいずれかに送ってやるだけで、音楽に関する処理を済ますことができました。 ここで注意していただきたいのは、初代ファミコンでは、ゲーム中に使用される効果音さえも、この4声のいずれかを使用して作られていたということです。 いよいよ次章からは、これまで見てきた制約の中で書かれた曲、限られた音色で作られたSEの数々を解説していきます。 |