
| 3声でスゥイング 〜スーパーマリオ・ブラザーズ |
|
『スーパーマリオ・ブラザーズ1(任天堂)』より。 洗練されたキャラクターに秘密の通路、アイテム取得により技量も変われば自らの大きさまで変わってしまう主人公。 長い冒険の旅を盛り上げる数々の要素は、独特にして明快な世界観とあいまって、この作品を世界中で大ヒットさせ、後に続く横スクロール型アクション・ゲームの模範となるに至りました。 もちろんBGMにおいても、名作に相応しい工夫が随所に凝らされているのが目に付きます。 しかし、聴くほどに、この曲がどのジャンルに属するのか分からなくなります。リズムはジャズのようでいて、響きは陽気なラテンの雰囲気。曲の怪しさだけをとったら、怪作『(ビート)たけしの挑戦状(タイトー社)』とまともに張り合える、数少ない作品の一つに思えてくるのは、わたしだけでしょうか? |
聴く→midi file4kb) 楽譜 | 和声的関心 | リズムの用法 | 極めつけはコレ
とりあえず、はじめの数小節を見てみましょう。

|
上から順に、 |
ドラムパート |
|
のっけからセコンダリー・ドミナント[ II(VofV)→V ]。 参考までに、[ドミナント周辺に始まる2小節のイントロ]は、わずかながら形状を変えつつ、同シリーズ3作目及『スーパーマリオランド(GB)』に引き継がれました。ただし、ループのラスト2小節がイントロと重複する1作目と異なり、他の作品では、あくまでイントロとして一度目のループのはじめに流れるだけです。 ボイスの配分: 上記の楽譜にはない中盤以降、3声の役割は、主旋律+ハモリ+ベースラインとなります。このように一曲を通して3声の使い方を変化させることは、曲の展開が単調になるのを防ぐのに、最も有効な手法の一つです。 |
|
上記の楽譜では便宜上省略したのですが、ドラム・パート「のみ」、実際には8分音符はすべて8分3連で刻まれています。 このパートに普通の8分音で進行する他のパートを重ねると、タイミングに1/6拍ほどのズレが生じます。 このズレが、曲のノリを保ちつつ、どことなくユーモラスで砕けた雰囲気を醸し出すのに一役買っているようです。 |
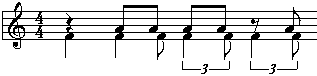
| サンプルのmidiファイルに収録してある通り、この曲に出てくるドラム・パターンは、2小節のものが二つだけです。中盤以降は、はじめの2小節が延々と繰り返されています。何か意図するところがあったのか、それとも締め切りが近かったのか... |
下に示すのは、この曲中に出てくるコードに共通して見られる、特徴的な波形です。
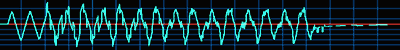
|
ご覧のように、最初の数ミリ秒ほど、波形が正確な三角を描いていますね。 これは、ベースが他のパートより少し早目に入ってきていることを示しています。 一見すると同じリズムを刻んでいるようでいて、実はルーズな上段3声。これとは逆に、タイトに打ちこんだデモのmidiファイルをお聴きになって、何か物足りなく思われたようでしたら、このズレの不在が多いに関係していると思われます。 これらの点だけを見ても、この曲が苦しいながら、どこかほのぼのとしたマリオの世界を縁取るのに、いかに成功しているかがお分かりいただけることと思います。 |